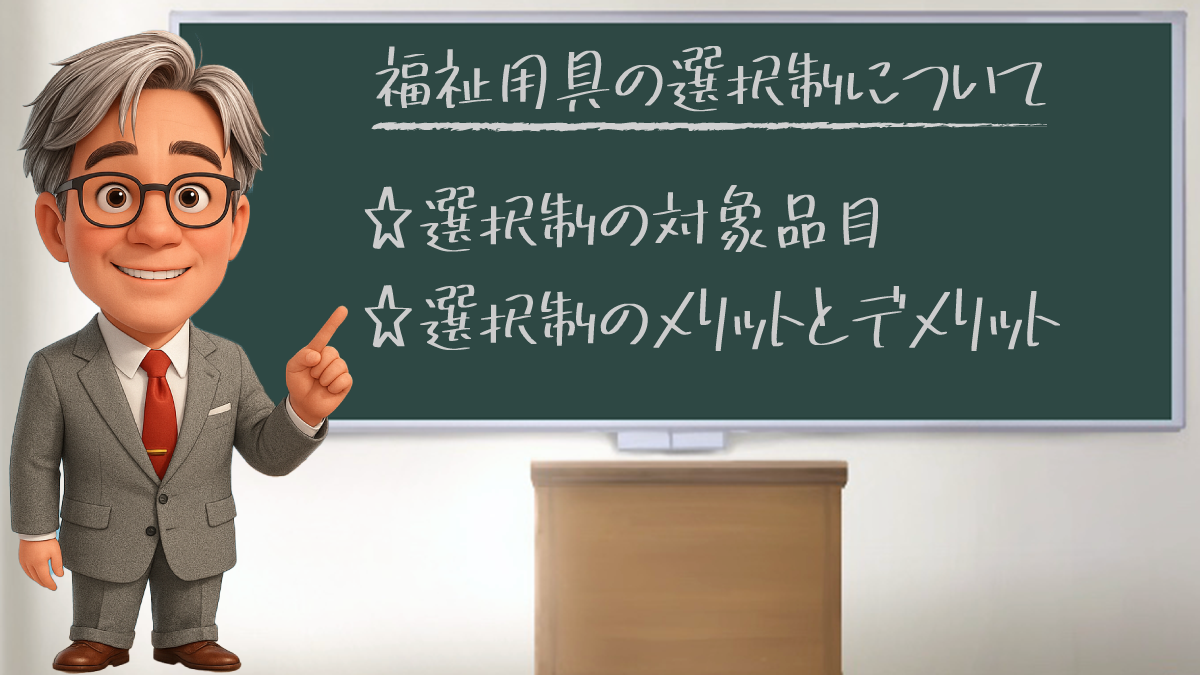~介護保険制度改正による福祉用具の選択制について~
2024年度の介護保険制度改正により、福祉用具の一部に「選択制」が導入されました。
この改正は、福祉用具の利用における効率性と公平性の確保、さらには介護サービスの質の向上を目的とした重要な変化です。
本記事では、福祉用具の選択制に関する基本情報から、対象品目、制度導入の背景、利用手続き、メリット・デメリットまでを出来るだけ分かりやすく解説します。
福祉用具の「選択制」とは?
選択制とは、利用者が複数の福祉用具の中から自分に合ったものを選べる制度であり、事業者が一方的に用具を指定するのではなく、利用者の希望と状況に応じて柔軟に選定できる仕組みです。
これにより、用具の価格や機能、使い勝手などを比較検討し、より適切な選択が可能になります。
選択制の対象品目
対象となる13品目の中で選択制が導入されている品目(2024年改正時点)
| 分 類 | 品目名 |
|---|---|
| 移動支援用具 | 車いす(普通型・介助型)、車いす付属品 |
| 入浴支援用具 | 入浴用いす、浴槽用手すり、入浴台、すのこ |
| 排泄支援用具 | 腰掛便座(補高便座含む)、ポータブルトイレ |
| 転倒予防用具 | 歩行器、歩行補助つえ(4点杖など) |
| ベッド関連 | 特殊寝台、特殊寝台付属品 |
選択制導入の背景と目的
選択制の導入には、以下のような背景と目的があります。
選択制導入の背景
利用者ニーズの多様化
同じカテゴリの用具でも利用者の身体状況や生活環境によって適した製品は異なります。
価格のばらつき
同じ機能を持つ製品であっても価格に差があることから、適正な価格競争を促す必要性。
事業者による提供の偏り
特定のメーカー製品に偏るケースが多く、選択肢が制限される懸念がありました。
選択制導入の目的
利用手続きと留意点
手続きの流れ
- Step1ケアマネジャーとの相談
- Step2複数の候補機種・価格の提示(事業者より)
- Step3比較検討
- Step4利用者による選定・同意
- Step5貸与または購入開始
留意点
説明責任
事業者には、価格・仕様の違いを利用者に丁寧に説明する義務があります。
公平な比較資料
同等機能を有する製品での比較表の提示が求められています。
価格透明性
貸与価格の開示、同一製品での地域差是正が進められています。
選択制のメリットとデメリット
| メリット | デメリット |
|---|---|
| 利用者の希望や身体状況に合った製品を選べる | 製品比較や選定に時間と知識を要する |
| 貸与・購入価格の透明性が向上する | ケアマネ・事業者の負担が増加する可能性 |
| 適正な価格競争が促進される | 利用者が情報を十分に理解できない場合も |
Tips

福祉用具の選択制は、利用者の視点に立った制度改革の一環として、非常に意義深い取り組みです。
今後はさらに対象品目の拡大や、情報提供の質の向上が求められます。
ご自身やご家族が福祉用具を利用する立場にある方は、制度を正しく理解し、納得のいく選択ができるよう、専門職との連携を大切にしましょう。